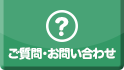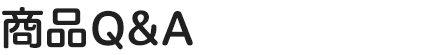商品Q&A
野菜・果物
-
たけのこ水煮に青カビのようなものが発生しています。
たけのこ表面の節の部分にある、イボ状のところどころが緑色を帯びてました。これらの現象は生育が進んだ大きいものに見られ、若いたけのこにはあまり発生していませんでした。たけのこは、成長が進むにつれてイボ状部分にポリフェノール誘導体が溜まります。そしてこれを水煮する際に、使用する金属食器から出る金属と、ポリフェノール誘導体が反応を起こし暗青色になることがあります。水煮にはよく発生する現象であり、心配するようなものではありません。
-
『ブロッコリー』軸に黒っぽい斑点が・・・・
現品の状態から、生育中に気温が低い日が続き、養分の吸収に影響が出たことが考えられます。ホウ素欠乏症による生理障害により斑点が発生したものでしょう。病気や腐れではありませんので食べても問題はありませんが、産地には斑点の著しいものの選別排除を要請しました。

-
『ごぼう』切ると、中心がピンク色に・・・・
ごぼうにはポリフェノールの一種であるクロロゲン酸が含まれています。クロロゲン酸は空気にふれると酸化してピンク色になることがあり、その度合いは生育時に含まれるクロロゲン酸の量によって強弱があります。今回はクロロゲン酸が多く含まれていたことで起こった現象です。害はありませんので、安心してお召し上がりください。

-
『じゃがいも』中身が変色している・・・・
現品の状況から、生理障害の一種と考えられます。生育中に土壌水分が不足したものがあり、果肉細胞が影響を受けて黒褐色の斑点が現われたようです。食されても害はありませんが、食感が悪くなります。外観からの確認が難しいため袋詰めされてしまいましたが、産地での選別強化を要請するとともに、引き続き農産加工センターで抜き打ちでのカット点検をおこないます。今後もこのような商品がありましたらお申し出ください。

-
『ほぐしめじ』緑色の物が付着している・・・・
現品の状況から生育棚に発生したアオコ(藻類)が付着したものと考えます。しめじは湿度が約100%の室内で栽培するため、アオコが発生しやすい環境にあります。定期的に生育棚の清掃はおこないますが、見落とした部分が選別や包装段階で発見できなかったものと思われます。生育室内、生育棚清掃の徹底と、選別や包装時の点検強化を指導しました。なお、万が一このような商品があった際は、お手数ですがお申し出ください。お取り替えいたします。
-
『じゃがいも』表面が緑色に。食べても大丈夫?
じゃがいもが緑化する原因には、栽培中の雨などで覆っている土がずれて日光が直接あたることや、収穫後から使用までの間に、電灯の灯りなどにさらされた場合が考えられます。緑色になること自体は光の影響で葉緑素が生成されたためで、これについては問題ありませんが、同時にソラニンという成分が生成されます。ソラニンはエグ味を感じますので、多量に摂取する可能性は低いと思われますが、多量に摂取すると腹痛や吐き気を催します。このようなじゃがいもを調理する場合は、皮を厚めに剥き、特にソラニンは芽に多く含まれますので、この部分を大きくえぐり取る必要があります。取引先へは選別時の目視確認により緑色化したじゃがいもは取り除き、保管中に光に長時間さらされることのないよう要請しました。お届け後も直射日光を避け、できるだけ暗い場所での保管をお願いいたします。
-
『りんご』切ると、内部が褐変(茶色く変色)していた。
りんごは11月中に収穫をおこない、低温管理することで長期の貯蔵が可能ですが、果肉に蜜がある場合は、その部分が褐変(茶色く変色)したり柔らかくなることがあります。産地でのセンサー選別や、農産加工センターでの抜き取り点検をおこなっておりますが、すべての排除が難しくご迷惑をお掛けしました。同様の状況がありましたら、お申し出ください。
-
『ブロッコリー』紫色っぽい色。食べられるのか心配・・・・
現品を確認したところ、ご指摘のように花蕾(からい)が通常より全体的に濃い紫色っぽく感じられました。この原因は、ブロッコリーやキャベツなどアブラナ科の植物に含まれる成分であるアントシアン色素が、生育中の気温低下で次第に紫色やピンク色っぽくなるためです。栽培中の気候条件の影響受け、アントシアン色素の影響を受けることがありますが、茹でると緑色になり、味は変わりません。ご安心の上、お召し上がりください。
-
『里芋』煮ても、中まで味がしみ込まない。ゴリゴリして硬い・・・・
これは、「ゴリ芋」と呼ばれる生育不良の芋です。地上部の葉が何らかの原因で崩壊した場合に、親芋や子芋の養分が孫芋に移り変わってしまって、芋の貯蔵澱粉がなくなってしまった状態です。また、生育中に高温や干ばつによって里芋にストレスが発生すると、水分がないカスカスした状態や、ゴツゴツして固いものが発生することもあるようです。本来、これらの「ゴリ芋」は除去されなければいけないのですが、外観からは見分けにくいために除去し切れず混入したと考えます。産地には生育中の地上部の確認や抜き取りによって、混入防止に努めるよう申し入れました。
-
『れんこん』茹でると赤く染まった。薬品を使っているから?
現品は所々が赤くなっていましたが、芯の部分に変色はなく、「芯とおし」と言われる病気や、腐敗したものではありませんでした。れんこんにはポリフェノールの一種である「タンニン」が含まれています。この「タンニン」は、熱を加えたり酸化すると、赤・紫・黒・褐色などに変色することがあります。また、使用する調理器具などに鉄製品がある場合や、れんこんが生育した土中の鉄分が変色を助長することが知られています。実際に商品をカットして湯がいてみた結果では、紫色に近い状態で変色しましたが、個体差があるようです。れんこんは「無漂白」の商品であり、変色しても無害ですが、調理の際にカットしたれんこんを酢水(酢は2%)でアク抜きしていただきますと、変色しにくくなります。ぜひ、おためしください。
-
にんじんが包丁が入らないくらい硬い
今回のご指摘は、「とう立ち」という生理現象によるものと思われます。これは暖かくなると花芽が出てくる現象で、他の野菜でも見られます。花芽を伸ばすための栄養が可食部分からとられるために、中身が堅くなったり、スポンジ状になってしまいます。産地では降雨の後、晴天により日中気温の高い日が続き、にんじんが急激な生長をしたことから、とう立ち果が発生しました。生産者が花芽を見落としたため、問題のない商品に混入して出荷されたものと考えられます。生産者に注意を呼びかけ、収穫時の確認の徹底により混入防止に努めます。
-
『アボカド』購入してから2週間。いまだに皮も固く、熟していない・・・・
アボカドは樹上で熟すことがなく、収穫後に追熟する作物です。ただし、追熟の温度には注意が必要で、低すぎても高すぎても変色します。収穫後、移送や通関を経て約3週間程度で国内に入荷しますが、この時は青く硬い状態です。取引先加工場では、1玉ずつ外観の確認・抜取りでのカット確認をおこない、お手元に届くころ食べ頃となるように追熟する努力をしています。また、ならコープ農産加工センターでも外観の確認、抜取りカット確認をおこなってお届けしています。しかし、アボカドにも個体差があり、色の付きにくいものや色の付きやすいもの、追熟が早いものから遅いものがあります。今回お届けした商品は、果肉に含まれる脂肪含量が少ない傾向にあり、より追熟が遅くなっていることが考えられます。ご迷惑をおかけし、申し訳ございません。以下はアボカドの保管、温度帯の目安です。
●4.5度~5.5度・・・・・・・・・・・・・・・・・保管
●8.0度~12.0度・・・・・・・・・・・・・・・・ゆっくり追熟
●14.0度~21.0度・・・・・・・・・・・・・・最適な追熟温度
表皮の色が全体的に茶色くなって、ヘタ部分を指で押すと少し柔らかくなったぐらいが食べ頃です。 -
『宮崎のごぼう(カット)』黒いスジがある・・・・
現品を確認したところ、ごぼうのところどころに黒くスジ状になった部分が見られました。生育中に大雨の後、畑の低地に雨水が溜まりごぼうが冠水し、部分的に酸欠になったり、土中の微生物の影響受けたことで変質した症状であることがわかりました。
●今後の対策●
(1)出荷前、ごぼうをカットした際に断面をよく確認します。
(2)症状が見られた畑のごぼうは点検確認します。
(3)今後の栽培時には畑を整地して排水を良くすることで発生防止に努めます。 -
『白菜』葉にカビのような黒い点が・・・・
この黒い斑点は、「ゴマ症」と呼ばれる生理障害です。白菜の白い軸の部分に多数の黒い斑点が現れ、お問い合わせをいただくことがあります。病原菌などによる症状ではなく、また、カビや虫害でもありません。白菜自体がもつ生理反応によるもので、微量栄養素の過不足でおこります。ただし、チッソ分をはじめ多数の微量栄養素が関係しているため、原因の特定は困難です。品種によって症状の差が大きく、また、園地によっても発生率が異なります。健康に問題はありませんので、安心してお召し上がりください。
-
『大根』切ると青くなっていた・・・・
今回のような生理障害は、地温・気温との関係が強く、栽培後半の平均気温が25℃を超える日が続いた場合に見られるものです。大根を切った際に中が黒くなったり、青いしみのようなものがある場合があります。食べても問題はありませんが、苦味を感じる場合があるようです。通例、農産加工センターでは、抜き取りでカット・断面の確認をおこないますが、今回は1本まるごとでのお届けでした。今後も抜き取りでのカット確認を続けますが、生理障害果は外観に腐敗などの症状が見られる病気の発生とは異なり、見た目で判断することは非常に困難です。ご迷惑をおかけしましたが、この点をご了解いただけますようお願いします。
-
『さつまいも』蒸したら皮の内側が緑色に・・・・
現品を確認したところ、緑色っぽく変色した部分が見られました。さつまいもやごぼうには、ポリフェノールの一種であるクロロゲン酸が含まれています。クロロゲン酸は、アルカリ性物質の影響で、食品中の他の物質と反応して緑色の物質に変化することが知られています。たとえば、衣に重曹を使用したさつまいもの天ぷらや、ごぼうとこんにゃくを一緒に煮込んだ場合など、緑変することがあります。これは重曹やこんにゃくのアルカリ性物質の影響で、クロロゲン酸が他の物質と反応し、緑色の物質を生成するためと考えられています。また、クロロゲン酸変色の原因物質が特定できない場合でも、何らかのアルカリ性の物質が関係していることもあるようです。冷蔵庫で保管中に、他の食品から発生したアンモニアガスなどで、保存中の蒸したさつまいもが緑変したという事例もあります。今回も、こうしたことが原因で緑変してしまったと考えられます。
-
『すいか』食べたら舌がピリピリ・・・・
今回の原因には次のような事が考えられます。
(1)モザイクウイルスによる病理的な場合。果肉全体が湿潤状態で黒っぽい赤(紫)色になり、食味がピリピリとすることがあります。
(2)生育中に強い直射日光にさらされたことによる異常高温による障害の場合。果肉内部の温度が上昇して糖度が上がらないまま成熟するため、肉質が変化します。特に根が弱っていたり、葉数が少 なかったりすると光合成機能が低下、また、乾燥 状態が伴うことで葉がしおれて果肉部にピリピリ感が発生します。
いずれも、抜き取り検品での確認をおこないながらお届けしていますが、100%発見することは困難であるのも実状です。ご理解をいただきますようお願いします。 -
『男爵いも』中に空洞が・・・
この症状は「中心空洞」といわれ、大型のじゃがいもに出やすいといわれています。空洞にはいくつかの種類がありますが、いずれも外観から発見することはできません。原因はじゃがいもの急激な肥大で、多雨や株間が広すぎる事などが考えられます。小さいいもに空洞が出来る場合は急激な水分の流入が考えられます。また、裁培園地の微量栄養素(カリウム)の欠乏でもこの様な症状がでやすくなるようです。外観からは発見できず、出荷時にじゃがいもを抜き取ってカット、不良果の発見に努めていました。しかし、発見が難しい状況です。産地・加工場へは栽培地ごとに抜取ってさらにカット確認を強め、不良果の混入を防止するよう要請しました。